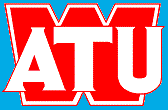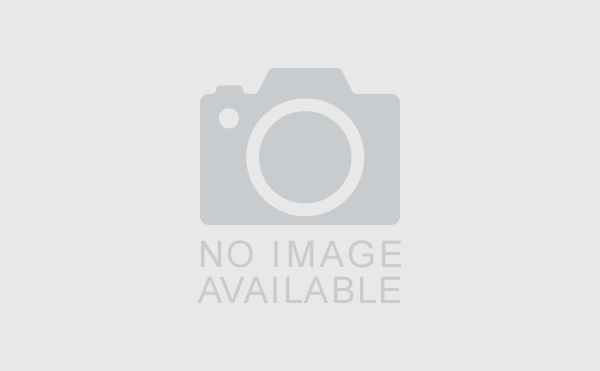2024.4.1号 No435 バイクの誘因事故に要注意――諦めずに事故後の対処の検討を――
■2024.4.1号 No435
バイクの誘因事故に要注意
諦めずに事故後の対処の検討を
N労組のMさんは昨年2月の営業中、新宿区大久保で明治通りを横断しようと中央線付近まで進行し、その際、左方向から片側2車線の左側端を通行してきたバイクを確認し、停車したところ、バイクが横転しました。
Mさんはバイクの自損事故だと思い込み、自分が誘因したとの認識がないまま、その場を立ち去りました。
その後、通行人の第三者からの通報でタクシーがバイクを撥ねて立ち去ったと新宿署に通報が入り、警察から会社に連絡があったため、Mさんは出頭することになりました。
新宿署では、ひき逃げ事件として扱っており、取り調べにより接触がないことは認められたものの、職業運転手としてけが人を前にして通報・救護義務を怠ったことを厳しく責められました。
Mさんはその点について反省し、供述書に署名をしました。
その結果、接触のない誘因事故による刑事処分と行政処分41点(救護義務違反35+軽傷人身事故6点)との通告を受けました。
組合法対部は会社の事故係に検察の事情聴取までに被害者との示談を早期に成立させるよう要望。物損事故示談書と人身事故示談予定書を取り交わさせ、検察庁には法対部長が付き添い、Mさんとともに提出しました。
それにより、刑事処分は不起訴処分となり免れることができ、罰金も発生しない処分となりました。
しかし、行政処分41点(免許取り消し、欠格期間4年)の嫌疑が残り、刑事処分と判断が異なる可能性もあり、予断を許す状況にはなく、組合法対部は顧問弁護士に相談。不起訴処分告知書を取り寄せて不起訴内容が嫌疑不十分であることを確認したうえで、嘆願書の署名活動に取り組み、嘆願署名を携えて聴聞会出席に備えました。
しかし、聴聞会の前日に出頭を停止して改めて検討するとの連絡があり、その後「2点の加点をする」違反内容は「交差点安全通行義務違反」との通知が届き、Mさんは事なきを得ることができました。
【東京地連・道交法対策委員会】